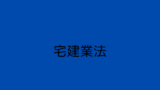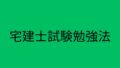制限行為能力者とは?
制限行為能力者とは、未成年者や精神上の障害を持つなど、法律行為を単独で行うには判断能力が不十分とされる者を指します。この制度は、彼らを保護し、不要な不利益を被らないようにするためのものです 。
宅建試験では、制限行為能力者に関する出題頻度が高く、得点源となる分野です。以下では、この重要テーマを徹底的に解説し、試験対策に役立つポイントを紹介します。
制限行為能力者の種類と特徴
制限行為能力者には以下の4つの分類があります。それぞれの特徴を具体例とともに確認していきましょう。原則、制限行為能力者の法律行為は取り消しできます。
1. 未成年者
• 対象: 18歳未満の者
• 法定代理人: 親権者または未成年後見人。
• 取り消せる行為:
• 未成年者が単独で行った法律行為は、原則として取り消せます。
• 例外として、以下の場合は取り消せません:
- 保護者の同意があった場合 。
- 単に権利を得る、または義務を免れる行為(例: 贈与を受ける場合)。
- 保護者が営業を許可した場合、その営業に関する行為 。
• 試験の重要ポイント:
• 「営業を許可された未成年者は、成年者と同様の行為能力を有する」ことを理解しましょう 。
2. 成年被後見人
• 対象: 精神上の障害により判断能力を欠く者(常況にある者)。
• 法定代理人: 成年後見人。
• 取り消せる行為:
• 日用品の購入などの行為は取り消せません(民法9条)。
• それ以外の法律行為は、原則取り消すことができます。
• 重要ポイント:
• 成年被後見人は、成年後見人の同意を得た行為であっても取り消せます。(成年後見人に同意権はありません)
• 例えば、成年被後見人が土地を売却した場合、後見人、成年被後見人はその売買契約を取り消すことが可能です 。
3. 被保佐人
• 対象: 判断能力が著しく不十分な者(成年被後見人ほどではない)。
• 法定代理人: 保佐人
• 取り消せる行為:
• 「重要な行為」については、保佐人の同意が必要。同意がない場合は取り消せます。
• 例: 不動産の売買、借金、贈与、裁判、相続の放棄など 。
• 日用品の購入や日常生活に関する行為は取り消せません。
• 試験対策のポイント:
• 保佐人の事前同意がある場合、取り消せないことを理解しておきましょう
また重要な行為のうち特定の法律行為について、家庭裁判所の審判により保佐人に代理権を与えることもできます。
4. 被補助人
• 対象: 判断能力が不十分な者(被保佐人ほどではない)。
• 法定代理人: 補助人
• 取り消せる行為:
• 家庭裁判所が「重要な行為」の中から特定の行為について審判を下し、補助人の同意を必要とした場合、その同意がない行為は取り消せます。
• その他の行為は取り消せません 。
• 試験の注意点:
• 被補助人は他の制限行為能力者に比べて経済的判断能力が高いことを押さえましょう。
制限行為能力者保護と相手方保護のバランス
制限行為能力者の保護だけでなく、相手方も守るための制度が設けられています。
相手方保護の制度
- 催告権(民法20条・21条)
- 相手方は、制限行為能力者やその法定代理人に対し、契約を追認するか取り消すかを確答するよう求めることができます。
- 保護者に対して催告を行った場合や制限行為能力者が行為能力者となった後に催告された場合、期限内に確答がない場合、追認したとみなされます 。(取り消されるまでは有効な法律行為なので、取り消しができる人間が取り消し権を行使しないということは、有効のままでよいということです。)
- 被保佐人や被補助人が保佐人や補助人の追認を得るべき旨の催告されたにもかかわらず、その期間内に追認が得られない場合は、取り消したものとみなされます。(成年被後見人にはこの制度はありません)
- 詐術を用いた場合:
• 制限行為能力者が自らを行為能力者であると偽った場合は、取り消しが認められません 。
まとめ
制限行為能力者に関する知識は、宅建試験での得点源になるだけでなく、実務でも役立つ重要なテーマです。各制度の特徴を具体例とともに押さえ、過去問や模擬試験で繰り返し演習することで、確実な得点を目指しましょう。
さらに詳しい過去問解説は、こちらのブログで随時更新中!宅建士合格を目指して一緒に頑張りましょう!