宅建士試験を目指すみなさん、いざ勉強を始める際に「何から手をつければいいのかわからない」と感じることはありませんか?特に、最初の一歩を踏み出すのは大きな挑戦です。しかし、その第一歩をどう踏み出すかが、合格への鍵を握ります。
勉強の第一歩:自分の「わかる」と「わからない」を把握する
多くの人が、「全然勉強していないから」と考え、問題演習を後回しにしがちです。しかし、これは非常にもったいないことです。問題が解けないことを恐れず、まずは問題集に取り組むことが重要です。
なぜなら、勉強の最初のステップは、「自分が何をわかっていて、何をわかっていないのか」を明確にすることだからです。これをせずに、ただテキストを読み込むだけでは、効率的な勉強にはなりません。
具体例:宅建士試験における「わかる」と「わからない」の整理
例えば、宅建士試験の「民法」の分野で考えてみましょう。
- 問題を解いてみる 最初は解けなくてもかまいません。問題を解く中で、自分が「理解できている部分」と「つまずいている部分」が見えてきます。
- つまずきを記録する 問題演習を通じて、「どの範囲で間違えたのか」「なぜ解けなかったのか」をメモします。この過程が、「自分の弱点を知る」ことにつながります。
- 復習ポイントを明確にする 解けなかった問題を中心に、テキストや講義動画で該当箇所を復習しましょう。この繰り返しが理解を深めます。
問題演習を後回しにしない理由
問題演習を後回しにすると、以下のようなデメリットがあります。
- 理解度が不明確なままになる 何を重点的に勉強すればよいのかが分からず、効率が悪くなります。
- モチベーションの低下 目に見える成果が出にくいため、やる気が続きにくくなります。
逆に、最初から問題演習を取り入れることで、「できること」と「できないこと」がはっきりし、勉強の計画を立てやすくなります。
まとめ:まずは行動を起こそう
宅建士試験に向けた勉強は、完璧なスタートを切る必要はありません。まずは「問題集に取り組む」という行動を起こし、自分の現状を把握することが大切です。
「何がわかっていて、何がわからないのか」を明確にすれば、勉強の方向性が見えてきます。そして、その方向性に沿って着実に進んでいくことで、合格が近づきます。
今すぐ、問題集を手に取って一歩を踏み出しましょう!
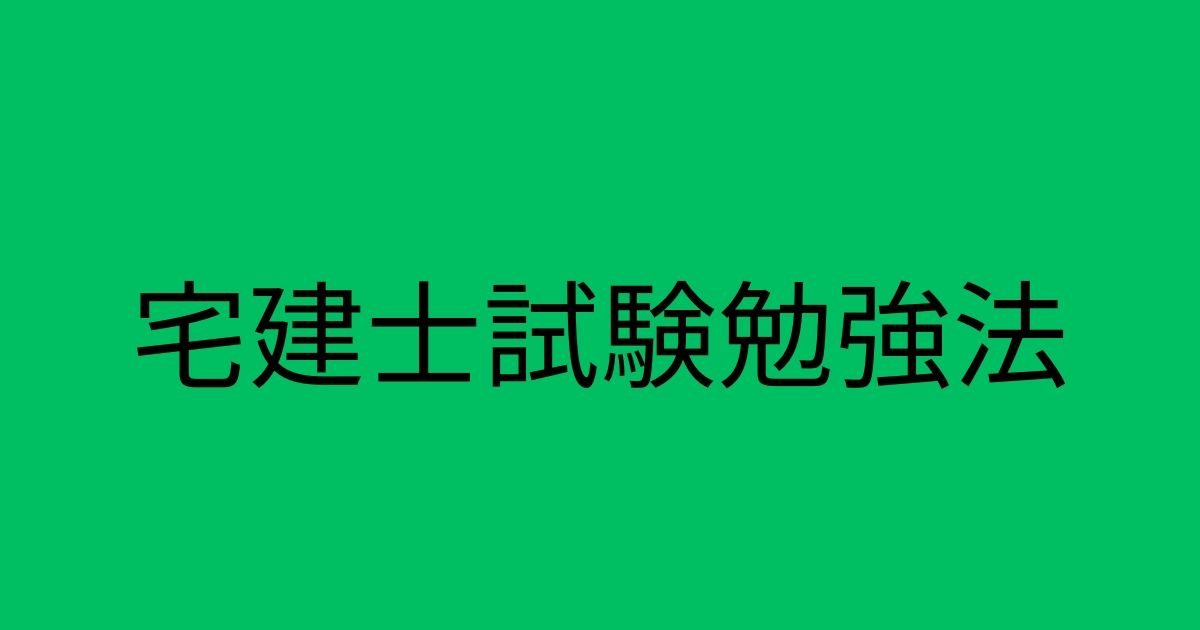
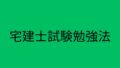
コメント